単身世帯の増加や物価高の影響などさまざまな要因の影響で申請が増えている可能性
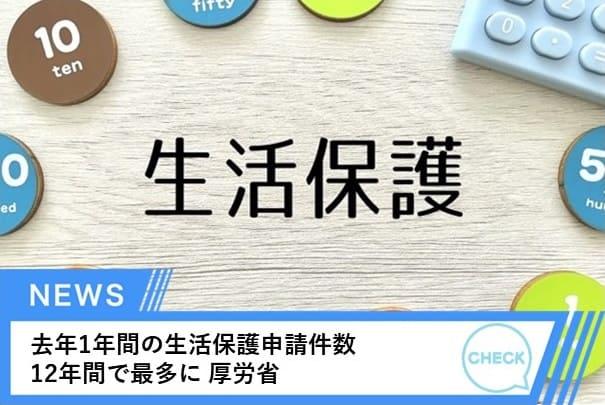
去年1年間の生活保護の申請件数は前の年より0.3%増えて25万件を超え、この12年間で最も多くなりました。
厚生労働省は「単身世帯の増加や物価高の影響などさまざまな要因の影響で申請が増えている可能性がある」とコメントしています。
厚生労働省によりますと、去年1年間に全国で生活保護が申請された件数は、速報値で25万5897件と前の年と比べて818件、率にして0.3%増えました。
生活保護の申請件数は、現在の方法で集計を始めた2013年以降で見ると、6年連続で減少し、新型コロナが感染拡大した2020年から5年連続で増加していて、比較が可能なこの12年間で最も多くなりました。
また、去年12月の時点で生活保護を受給している世帯は全国で165万2199世帯と、前の年の同じ月と比べて1579世帯、率にして0.1%減少しています。
特に高齢者の単身世帯が84万415世帯と、全体のおよそ半数を占めています。
厚生労働省は「単身世帯の増加や物価高の影響などさまざまな要因の影響で生活保護の申請が増えている可能性がある。
生活に困っている人はためらわず自治体の窓口に相談してほしい」とコメントしています。
専門家“低年金や物価高騰で預貯金取り崩し 要因か”
生活保護行政に詳しい立命館大学の桜井啓太准教授は、生活保護の申請が増えていることについて「単身の高齢者で低年金のため生活するのが難しいという人や、物価高騰の影響で預貯金を取り崩して生活している人が増えていることが要因として考えられる。
物価高騰が続けば、生活保護の申請は今後も増え続ける可能性があるのではないか」と指摘しています。
また、若者の貧困については「ここ最近、大企業を中心に初任給の引き上げなど賃上げの動きはあるが、非正規などの不安定な雇用の若者にはその恩恵は行き渡っておらず、物価高騰のダメージだけがのしかかっている。親世代や祖父母世代にも頼れなくなり、苦しんでいる現状があると思う」と述べました。
そのうえで「生活保護は2012年ごろに世間からのバッシングを受けてマイナスイメージが非常に強まった時期があり、いまだに『生活保護だけは受けたくない』という人がかなりいると思う。
ただ、困窮状態のままでいるというのは、その人にとってもダメージが大きいですし、生活保護の申請は権利ですので、困窮しているのであればすぐに自治体に相談してほしい」と話していました。
増える20代の受給者 支援団体“統計に表れない困窮状況も”
国が調べた年代別の生活保護の受給者数では、ここ数年、50代と70代以上とともに、20代が増え続けています。
都内のNPO法人と一般社団法人が行っている生活困窮者の支援でも、若い世代が対象となるケースが目立っているということです。
この団体は生活に困窮する人たちにホテルなどの宿泊チケットや非常食、モバイルバッテリーなどが入った「緊急お助けパック」を配布し、公的支援などにつなげる取り組みを行っています。
配布には住まいがなくこれまで利用したことがないといった一定の条件を設けていますが、ほぼ毎日、配布している状況だということです。
この取り組みを本格化させた2022年の利用者は125人でしたが、配布できる場所が増えたこともあって去年は倍以上の290人に増えました。
年代別で見ると、ことし1月までの半年間では20代から40代が全体のおよそ7割を占め、それぞれ25%ほどでした。
こうした人たちの多くが、給料が日払いの単発の仕事をしながらネットカフェを転々とする不安定な生活をしていたということです。
支援パックの利用後に生活保護を申請する人は半数ほどだということです。
ことし支援パックを受け取った30代の男性は、いわゆる「スキマバイト」で足をけがしましたが、病院にかかることもできないままネットカフェでの生活を続け、けがが悪化したところで支援を求めて訪れました。
男性はその後、足の治療を受け、生活保護の受給を始めたということです。
自身も10年余り前に生活保護を受給した経験があるNPO法人「トイミッケ」の佐々木大志郎代表(46)は、「スポットワークが普及し、きょうだけ働くということがすごく簡単になっている社会なので、毎日仕事を探して日銭を稼ぐ生活は繰り返そうと思えば繰り返せるが、一度、生活保護を受けて生活を立て直した方がよいのではないかと感じるケースは多くある。
統計に表れない生活保護の“半歩手前”という状況の若者も相当数いると思う」と話しました。
そのうえで「住まいという足場を作ることができれば、安定した仕事につけるという人は多いので、もう少し住まいに関する支援制度が利用されやすいものになってほしい」と話しました。
配信日:2025年3月5日
今回のこの報道に関して
2024年の生活保護申請件数が25万件を超え、過去12年間で最多となったことが明らかになりました。
厚生労働省は、単身世帯の増加や物価高騰の影響が申請増加の要因と分析しています。
特に、高齢者の単身世帯が全体の半数近くを占めており、低年金と物価高が厳しい状況を生んでいると考えられます。
また、20代の受給者が増えている点も注目されます。
非正規雇用の増加や賃上げの恩恵が行き渡らない現状が、若年層の困窮を深刻化させていると指摘されています。
支援団体の現場でも、日雇いやスキマバイトを続けながらネットカフェで生活する若者が多く見られ、統計に表れない「生活保護の半歩手前」の状況にある人々の存在が浮き彫りになっています。
生活保護制度には依然として「受けることへの抵抗感」が根強く残っていますが、支援団体は「困窮状態にあるならば迷わず自治体に相談すべき」と訴えています。
生活の再建にはまず住居の安定が不可欠であり、住宅支援を強化することで、より多くの人が安定した就労につながる可能性があると指摘されています。
今後、物価の上昇が続けば、生活保護の申請はさらに増加する可能性があります。
政府や自治体には、生活困窮者の支援制度をより利用しやすい形に整備することが求められるでしょう。