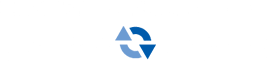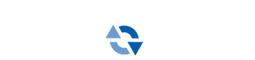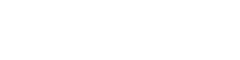不安や反対の声が多数

医療費が高額になった患者の自己負担を抑える「高額療養費制度」で、国が上限額の引き上げを決めたことについて、がん患者などで作る団体が28日会見し、不安や反対の声が多数寄せられているとして、国に引き上げの見直しを求めました。
高額療養費制度は、ひと月当たりの医療費の自己負担に上限を設けるもので、国は現役世代の保険料負担を軽減するため、ことし8月から上限額を引き上げることになりました。
具体的には、例えば年収およそ370万円から770万円の場合、今より8000円余り引き上げて8万8200円程度にするなどとしていて、その後も年収の区分をさらに細かく分けて段階的に一部の引き上げが行われます。
これについて「全国がん患者団体連合会」などが28日、厚生労働省で会見しました。
この中で、今月、患者や家族などにアンケート調査を行った結果、およそ3600人から回答があり、「治療を諦めなければならない可能性が大きい」など、不安や反対の声が多数寄せられたことを紹介しました。
そのうえで連合会の天野慎介 理事長は「今回の引き上げは継続して治療が必要な患者が多数いることを全く考慮しておらず、受診抑制や治療継続の断念などに直接つながるもので、国はすぐに引き上げを見直してほしい」と訴えました。
連合会では今後も、国に要望を続けていくとしています。
配信日:2025年1月29日
今回のこの報道に関して
高額療養費制度の自己負担上限額引き上げが、医療を必要とする患者にとって大きな不安要素となっています。
特に、がん患者団体などが訴えるように、長期にわたる治療が必要な人々にとって、この負担増は治療継続を難しくし、受診抑制につながる可能性が高いと言えます。
政府は現役世代の保険料負担軽減を目的として今回の改定を決定しましたが、医療費の自己負担増が患者に及ぼす影響への考慮が不足しているとの指摘は重要です。
例えば、年収370万~770万円の世帯で8,820円の負担増が生じるという数字だけを見ると、一見すると小さな変化のように思えます。
しかし、慢性疾患やがんなどで継続的な治療が必要な人々にとって、この負担増が積み重なることで、生活への影響が深刻化する可能性があります。
今回の患者団体の訴えは、単に経済的な負担だけではなく、医療へのアクセスそのものが制限されることへの危機感を示しています。
経済的な理由で治療を断念せざるを得ない状況が生まれれば、医療の公平性が損なわれるだけでなく、病状の悪化による社会的・経済的な負担増にもつながりかねません。
医療制度の持続可能性を考えることは重要ですが、それと同時に、患者の生活や健康を守るバランスも必要です。
政府は、こうした声に真摯に耳を傾け、医療費負担の在り方について、より丁寧な議論を進めるべきではないでしょうか。